ここでは、法務省が2025年12月に公表した、任意後見契約に関する公正証書を作成した公証人への調査結果(※)から、任意後見契約の本人や受任者の実態をみていきます。
任意後見契約は、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを決めておく契約です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
上記調査結果から、任意後見契約の本人の年齢をまとめると、表1のとおりです。

本人の年齢は、80代が最も多く全体の40.6%を占めました。次いで70代が28.8%となっています。70代以上で全体の81.7%を占めました。
受任者の年齢をまとめると、表2のとおりです。

50代が最も多く、全体の36.3%を占めています。次いで60代が25.2%、40代が19.5%となっており、40代〜60代で全体の81.0%を占めています。
受任者がどのような立場なのかをまとめると、表3のとおりです。

本人の4親等内の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他)が最も多く、全体の43.5%を占めました。なお、4親等内の親族の中では、子の割合が最も高くなっています。
ただし、本人の4親等内以外の親族を合わせても、親族の割合は50%にはならず、任意後見契約の受任者は、親族以外とするケースが多くなっていることがわかります。
任意後見契約を検討している方で、親族に受任者となる方がいない場合は、専門職や団体などを検討されるのもよいでしょう。
(※)法務省「任意後見契約に関する公証人の実態調査」
2025年8月〜9月に、任意後見契約の公正証書を作成する公証人に対して実施された調査です。2025年5月と6月に作成した公正証書における、本人や任意後見受任者の年齢、任意後見受任者の立場、任意後見契約の締結の動機等の任意後見契約に関する実態を調査したものです。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- ついに10%を超えた相続税の課税割合2026/01/20
- 減少に転じた配偶者居住権の設定登記件数2025/12/20
- 4年連続の増加となった相続税の新規発生滞納額2025/11/20
- 最近10年間で最多となった相続時精算課税の申告人員2025/10/20
- 減少に転じた暦年課税の申告人員数2025/09/20
- 成年後見制度の活用状況2025/08/20
- 相続税の簡易な接触件数は4年連続の増加に2025/07/20
- 利用が増加している相続土地国庫帰属制度2025/06/20
- 国外財産調書の提出件数は過去最高に2025/05/20
- 相続税の実地調査件数は3年連続の増加に2025/04/20
- 増加傾向にある自筆証書遺言書の保管申請件数2025/03/20
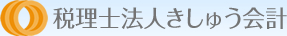






















 和歌山事務所
和歌山事務所